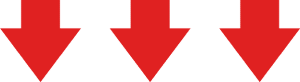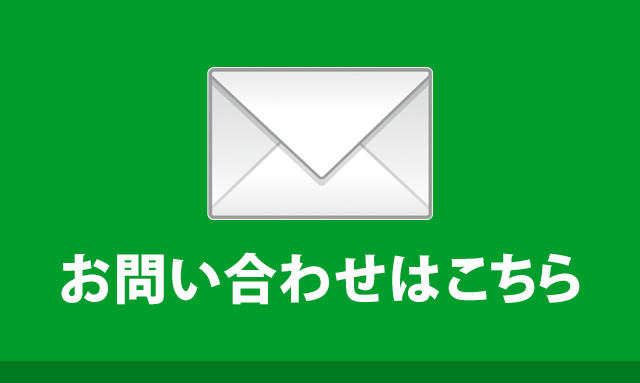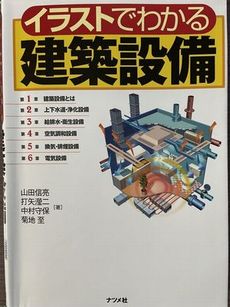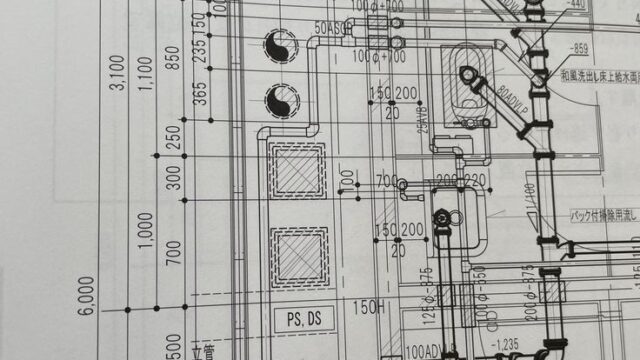» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
プレーイングマネージャーのジレンマ
あるクライアントのサブコンさんから、こんなご相談をいただきました。
「うちの会社の課長は部下を数人持っているのですが、自らも現場を担当しているため、
自分の現場の管理が忙しく、 部下の面倒まで見切れていないのが実情です。プレーイングマネージャーとしての職責は会社として果たしてもらいたいのですが、もう少し自分の 現場のマネジメントに費やす時間を少なくし、部下の管理に時間を多く取ってもらいたいのですが」
このような悩みは、どの会社でも多かれ少なかれ起こっているでしょうし、 会社の上層部の方たちの共通の悩みなのだと思います。
今回のこのクライアントさんの管理職研修を行うにあたり、課長さんたちの自分の受け持ち工事高がそのグループの全体の何パーセントであるかを算出してもらうことにしました。

現状の自分の受け持ち工事高は何%?
例えば A課長という人がいたとしましょう。 A課長のグループは部下が5人います。
昨年度のA課長グループ全体の工事高が2億だったとします。そのうち、A課長が担当している現場の工事高が1億だとすると、全体の50%ということになります。
A課長が大型物件を抱えている場合はそういうことが起こり得ます。
研修でこの数字をそれぞれの課長さんに算出してもらいましたが 、平均して出た数字は50%ぐらいでした。 だいたい予想していた通りの数字でしたが、この数字が示す実態としてやはり課長たちさんのプレーイングマネージャー度が高いということが伺えます。
受け持ち工事高の%を下げるには?
受け持ちの工事高というのは、単なる数字なのでなかなか実態を表すことは難しいと思います。大型現場の現場代理人で部下が数人いる場合と、1人で小規模の現場を1つ受け持っている場合とでは状況が違います。
今回の研修では、実際の数字というよりも課長さんたちに、今の割合の数字から例えば20%あるいは30%下げるにはどうしたらいいかを考えるための材料として、あえてこのような数字を出してもらいました。
会社としては、ある程度プレーイングマネージャーとしての職務は仕方がない。しかし、できることであれば課長さんたちにプレイはせずマネジメントに徹してほしいというのが本当の気持ちなのです。
現状、 今の受け持ち工事高のパーセントを極端に減らすということは難しいと思います。
ところが、日頃自分の仕事で精一杯の課長さんたちに一度立ち止まってもらい、どうやったら自分の仕事の時間を減らし、部下の管理のために使えるのかを考えてもらう時間を設けるのが研修の意図するところなのです。
自分たちで考えるマネジメント
研修では、正解ということは講師側からは提示できません。なぜなら、A課長さんのグループのことはA課長さんが一番よく知っているし、解決策も自分の中に持っているからです。それを考えてもらい、グループ内に変化を起こすことのきっかけ作りをしてもらうことが研修の目的だからです。
今回はワークで4人ずつのグループを4つに分けた班編成で研修を行いました。
その中で出た対策案として、 アウトソーシングできるものは振り分けし、外注に委託する。 部下とのコミュニケーションをより密に行い、部下の適性をよく把握し、判断した上で配置を考える。 なるべく仕事の内容に応じて権限委譲し、自分がマネジメントできる時間を確保する。部下に主体性を発揮できるように指導する。など、活発な意見が出てきました。
どれも当たり前といえば当たり前の内容ですが、日頃課長さんたちの頭の中には浮かんでこないことだったのではないでしょうか。マネジメントする事の重要性を知ってもらい、
それを実際に実行するきっかけとなれば、今回の研修は意味があったと思います。
まとめ
クライアントさんの役員様にお話を伺ったところ、外部のマネジメント研修に課長たちを参加させたのはよいが、他の会社から来ている人達は IT系や金融系の30歳前後の人が多く、建築業界の40代の社員がそこに行くとアウェー感がとても強く、何やら疎外感で、
研修の内容が頭に入らなかったということでした。
なかなか建築業界にマッチした外部研修というのは少ないでしょうし、この業界における管理職、マネジメント教育は一般論では語れない部分も多くあると思います。
実態に即した研修でないと、自分ごととして受け入れられないのではないでしょうか。
「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ
シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。
まずは、資料請求をしてみてください。
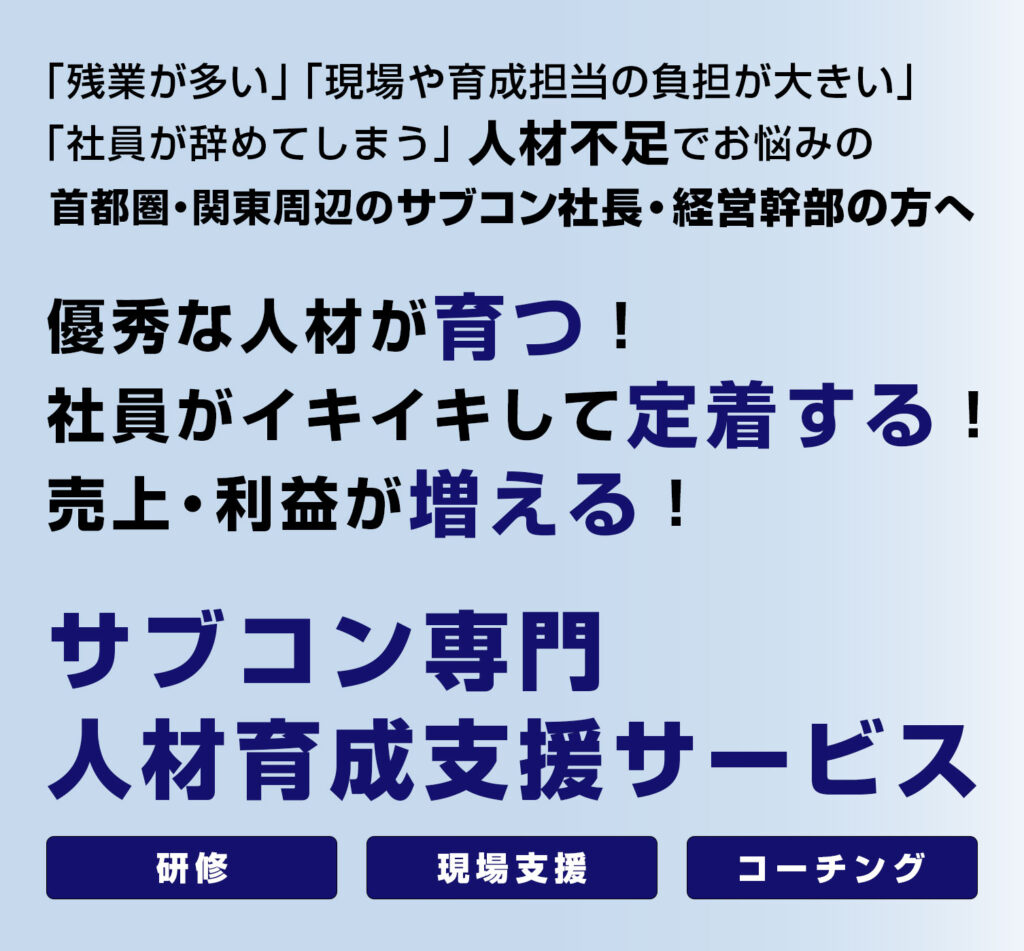
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。