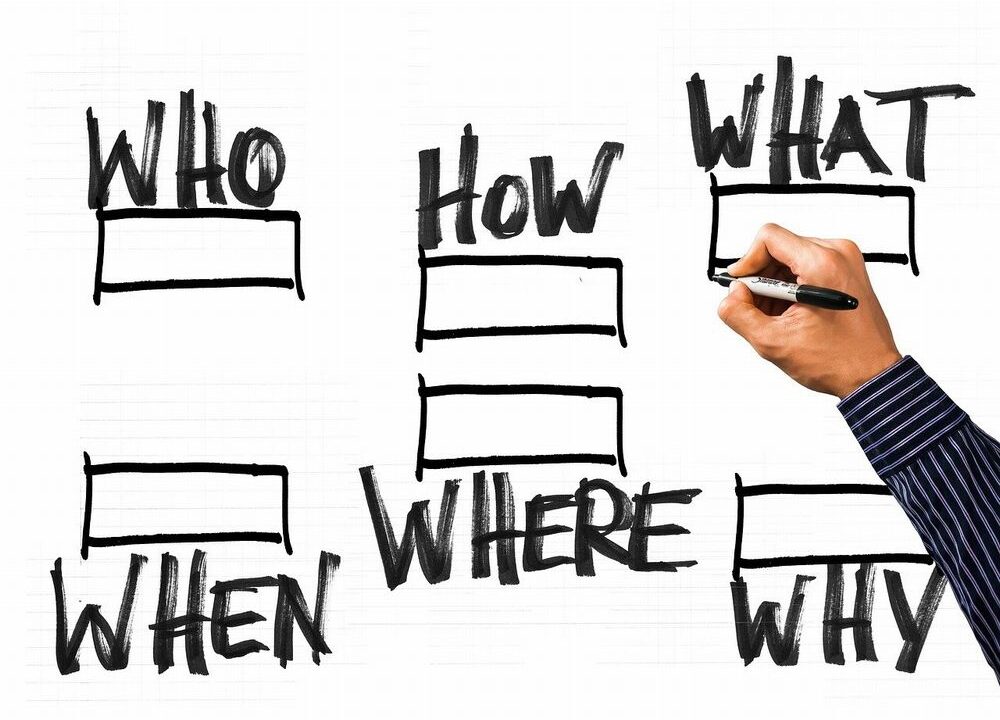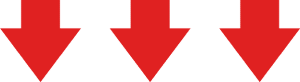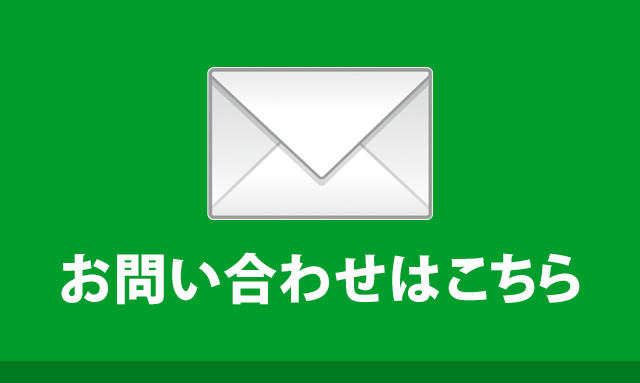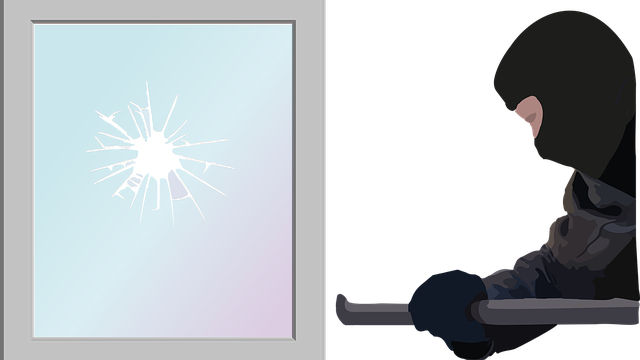あなたの会社では設備事故やトラブルが繰り返し発生し、客先へ迷惑をかけたことで工事部長や役員の方が頭を下げに行かなくてはならないという状況が多発しているということはありませんか。この記事では、設備事故を限りなく0にするための施策について、「失敗の科学」という書籍を参考に解説しています。
» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
設備事故・トラブルがなかなか減らない理由とは?
設備事故あるいは設備関連のトラブルというのは、多岐にわたります。空調、衛生機器本体のトラブル、機器廻りのメンテナンスの問題、ダクトからの漏洩、臭気、ガラリ廻りの騒音、配管からの漏水、ドレンパンからの排水のあふれ、異種金属による腐食、排水つまり、その他にも結露、温湿度が設計値に満たない機能不足などなど、建築設備はさまざまな事故、トラブルが起こる可能性を秘めています。
このような設備事故、トラブルを無くすためにはどうすればいいでしょうか。まず、設計段階から問題が起きそうな芽を極力摘んでおくということ。また施工着手段階において、設計ではカバーしきれない施工上での問題が起きそうなポイントをつぶすことも重要です。施工途中においても日々の品質チェックを怠らず、継続していくことは必要です。
設備事故、トラブルが減らない理由として、竣工までの施工管理を十分に行っているつもりでも、管理上での何かが不足していた、竣工後の使い勝手や環境の変化による要因などがあります。もう一つは、社内で過去の事故、トラブル事例が全社員に共有されているかということが上げられます。その会社の工事はある程度、規模、建物用途、新築か改修か、空調か衛生か、ガスか消火か、外構工事が多いなど、問題発生のパターンが近い場合が多いと思います。それらの多く発生するトラブル事例を共有し、問題を分析し、再発防止策を策定し更に共有すれば、トラブルは減っていきます。

「失敗の科学」から学ぶトラブル事例の活用
設備事故、トラブルを0にするために、参考になるのが、「失敗の科学」という書籍です。この本は、22ヶ国刊行の世界的ベストセラーでマシュー・サイドというアメリカの著者の作品です。
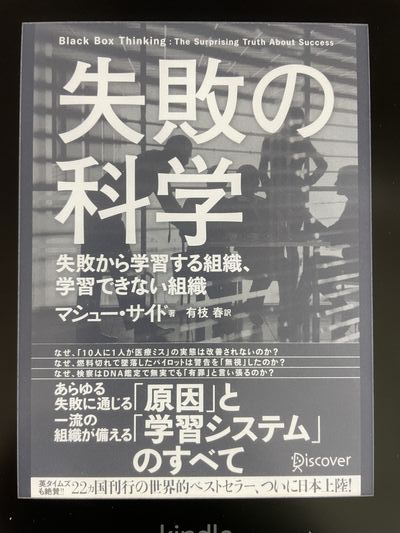
この本では、いろいろな事故や失敗の事例が紹介されていて、その背景や事故を起こした人たちの心理的なこと、組織的、社会的な問題を興味深く分析しています。ここでは、航空機事故に関する内容を抜粋して、ご紹介します。
航空機事故が起きると多くの尊い人命が失われるという、失敗が許されない世界であることは言うまでもありません。万が一事故が発生した場合、どう対処するのでしょうか。
航空機事故が起きると、航空機会社とは独立した調査機関、パイロット組合、さらに調査
機関が、事故機の残骸やその他さまざまな証拠をくまなく調査する。事故の調査結果を民事訴訟で証拠として採用することは法的に禁じられているため、当事者としてもありのままを語りやすい。こうした背景も、情報開示性を高めている要因だ。調査終了後、報告書は一般公開される。報告書には勧告が記載され、航空会社にはそれを履行する責任が発生する。事故は、決して当事者のクルーや航空会社、もしくはその国だけの問題として受け止められるのではない。その証拠に、世界中のパイロットは自由に報告書にアクセスし、失敗から学ぶことを許されている。
かつて米第32代大統領夫人、エレノア・ルーズベルトはこう言った。
「人の失敗から学びましょう。自分で全部経験するには、人生は短すぎます」 本文より引用
この本の抜粋での主旨は、航空業界の事故の歴史がそれを蓄積、分析、共有することで、劇的に事故を限りなく0に近づけることだったということです。
この本を読んだとき、私は建築設備業界における設備事故やトラブル撲滅もこの視点に立って、それぞれの会社が独自に事故事例をまとめ分析し、社内共有することを根気よくコツコツ積み上げていくことが必要と感じました。
トラブルが0になることで顧客満足度が上がる
航空業界は人命を預かることが使命だからここまで必死やっているのでは、我々のトラブルはそこまでシビアじゃないから、と思っていませんか。トラブルを繰り返せば、当然その会社の信頼が失墜し、お客様からも信用を失ってしまいます。だからこそ、設備事故、トラブルを0にする必要があるのです。
設備事故、トラブルが起こったことは恥ずかしいことではない、起こったことは仕方がないと受け止める社内環境を作り、社内全体で再発防止の行動を繰り返し、積み上げていけば必ず、事故は0になります。そうすれば顧客満足度が上がり、さらには社員の満足度も上がることでしょう。
まとめ
航空業界の事故後の再発防止対策から学び、建築設備における設備事故、トラブルをいかに0にするかのお話をしてきました。事故が起きたことのその後の対処をどうするかの重要性がお分かりいただけたかと思います。トラブルが起きたとき、「しまった、どうしよう」と慌てることなく、そのトラブルが今後の事故防止の材料になると考えて、今後の対策に活かせるようにしましょう。
「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ
シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。
まずは、資料請求をしてみてください。
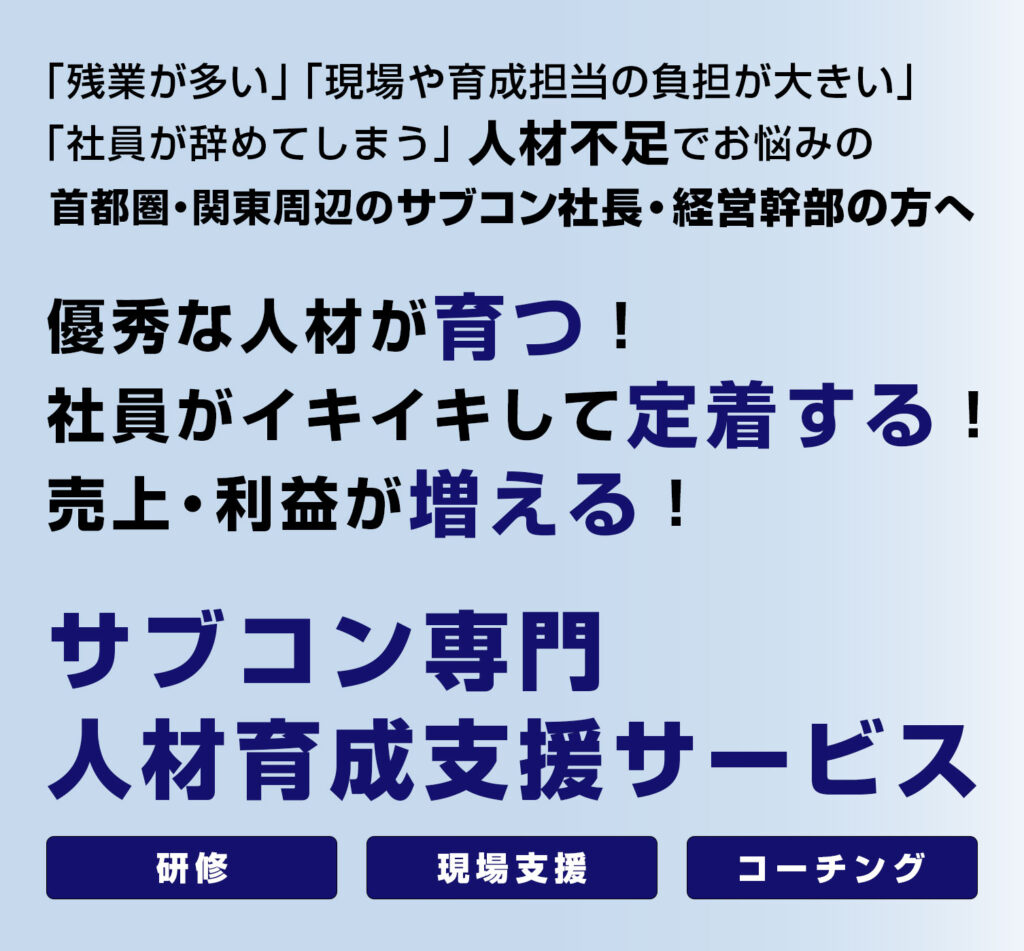
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。