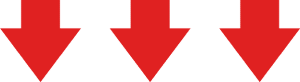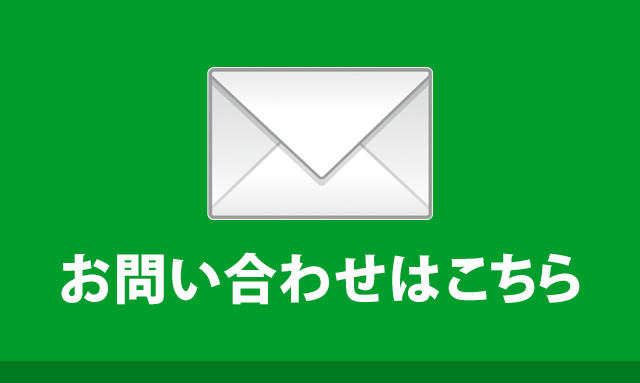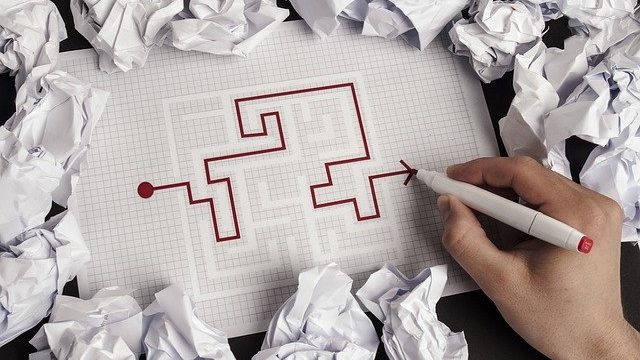» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
目次
建設業(施工管理)の離職率の現状
厚生労働省が毎年、新規学卒就職者の離職状況を公表しています。令和2年度における離職率は例年に比べ低下したとありますが、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者で36.9%、新規大卒就職者で31.2%という数字が発表されています。
これを産業別に見てみましょう。平成30年3月卒業者の場合、離職率が高い産業の1位から5位は、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、小売業の順となっています。5位の小売業が37.4%に対して、建設業は28%なので、上位産業から見ると数字は少ないですが、私のような業界に長く身を置く者にとって、決して建設業の離職率が少ないとは思えません。

若手施工管理者が会社を辞める理由
1.作業環境の問題
施工管理の場合、建築現場が仕事場所になるため、内勤者のように一ヵ所に決まった場所で長く働き続けることはありません。短ければ数か月、長くても2年ほどのスパンで現場が変わります。それに伴って遠隔地に出張したり、遠距離通勤になったりという制約があるのが現場勤務の特徴です。私の場合、役所の大型物件での現場代理人の資格の関係で、地方都市の現場に単身赴任で出張することが多かったです。
また、改修工事で事務所や店舗が休みのときに工事をしたり、また道路の埋設配管工事やクレーンでの楊重作業で道路を占有するため夜間工事をしたりと、時間的な制約もあります。
2.勤務時間が長い
先ほどの作業環境に関連しますが、作業時間が長いというのも辞める理由として上げられます。休日出勤や夜間作業でも時間数が割り増しになりますし、平日での勤務も仕上げ工事が始まり竣工までの期間は遅くまで残業することは日常的です。
新入社員のうちはなるべく定時で帰るように現場でも配慮がある場合が多いようですが、2年目以降になると現場事務所のみんなが残業していることもあり、早く帰りづらい雰囲気に吞まれてしまうこともあるようです。
残業の原因としては、工程の遅延で工期の後半にしわ寄せがくることや、品質管理や安全あるいは社内書類、写真整理などの事務作業が膨大にあることでしょう。
3.上司との信頼関係が希薄
どの業種であれ、会社を辞める一番の理由は人間関係であると言われています。毎日、一日の大半を仕事に費やしており、その時間の中で上司や現場の職人さんと良好な関係が築けていないとしたら、これは仕事が嫌になってしまうのは当然です。私も若い頃は鬼のような上司がいて、毎日のように怒鳴られていました。現場とはそういうものだと半ばあきらめていましたが、今はそんな上司がいたら大半は辞めていくでしょう。
現場では、上司が部下と定期的に教育という立場で対話するという場面はほとんど無いと思います。仕事上での段取りや施工の納まりのこと、安全や品質の会話はあっても、部下本人の気持ちや心の動きについて、上司は把握できていないことが多いです。
このような状況では、もし愛想のよい上司で表面的には良好そうな関係でも、心の底からお互い信頼関係が築けているかどうかは疑問です。
離職率を下げる3つの施策
1.環境の整備
施工管理における離職の理由を上げてみましたが、ではどうしたらそれを未然に防ぐことができるでしょうか。
まず、環境を整えることです。先ほど原因の一つでお話した現場が一定期間で変わることは業界の特質なので、このこと自体は変えられませんが、制限のある改修工事や出張現場は一人の人に偏らず、ローテ―ションするなどの配慮が必要です。また、現場の人員配置も人の能力を優先しがちですが、通勤の利便性も重視し、社員の働きやすさを考慮すべきです。
2.採用時点での正確な会社情報開示
新卒採用の際の会社募集要項には、休日については土日祝休み、完全週休2日制と書いていても、実際に現場配属になると実態はその通りに休めない場合があります。会社としては、なるべく優秀な人材が欲しいし予定する人数は確保したいという希望から募集要項にそのように書きたいでしょう。しかし、「それは原則で、実際現場は工期というものがあって、残業もあり休日出勤もあるけれど、その分の振替休日は現場単位で取得できるようにしている。そういう制約はあるが、それに勝る働き甲斐がある職場です」ということを開示するべきだと思うのです。休日に対する価値観は就業意欲に大きく作用するものなので、これについては採用前にきちんと双方で確認し合う必要があります。
3.1on1ミーティングの定期的な実施
最後のポイントとして最も重要なこと。それはコミュニケーションによる信頼関係の構築です。先ほど、現場では上司と部下の信頼関係が希薄であると書きましたが、どうしたら良好な関係を築くことができるでしょうか。
それは1on1ミーティングを定期的に実施することです。1on1ミーティングとは、現場の責任者である上司と部下が1対1で面談することです。それなら年に2回、昇給や昇格時のタイミングでやっているという会社や現場は多いと思います。しかし、それだけでは足りないし、また内容も上司から部下への一方的な指導的なことではダメです。
1on1ミーティングの要点として、
・少なくとも月1回のペースで実施する(できれば3週間に1回)
・上司からの指導ではなく、部下が8割話す感覚で上司は聴く
・上司は部下に、現状の仕事の進捗状況、課題、悩みをひたすら聴く
・それを聴いたら、上司は2割の分量でフィードバックする(決して批判しない)
まずはこの要領で上司の方は部下と対話してみましょう。これを定期的に行うことで、部下に変化が現れます。要点は「上司は黙って聴く」です。
この1on1ミーティングを定期的に実施する現場が一つでも増えれば、上司、部下の信頼関係が構築され、その会社は離職率が減ることは間違いないと思います。
まとめ
建設業、施工管理の離職率を下げるための施策をまとめてみましたが、どの産業、どの仕事であれ、根本的なところは人間関係であると思います。それが解決され、信頼関係が構築されれば、他の問題の多くは解決されるのではないかと思います。
特に現場は少ない組織の中での人間関係なので、部下はその現場の期間中は一人の上司に仕えなければならず、その上司の指導方法で決まってしまい、もし誤った指導方法であれば部下の成長に影響を及ぼすでしょう。だからこそ、1対1の対話を会社ぐるみで仕組み化し、上司の教育から始めることが必要です。
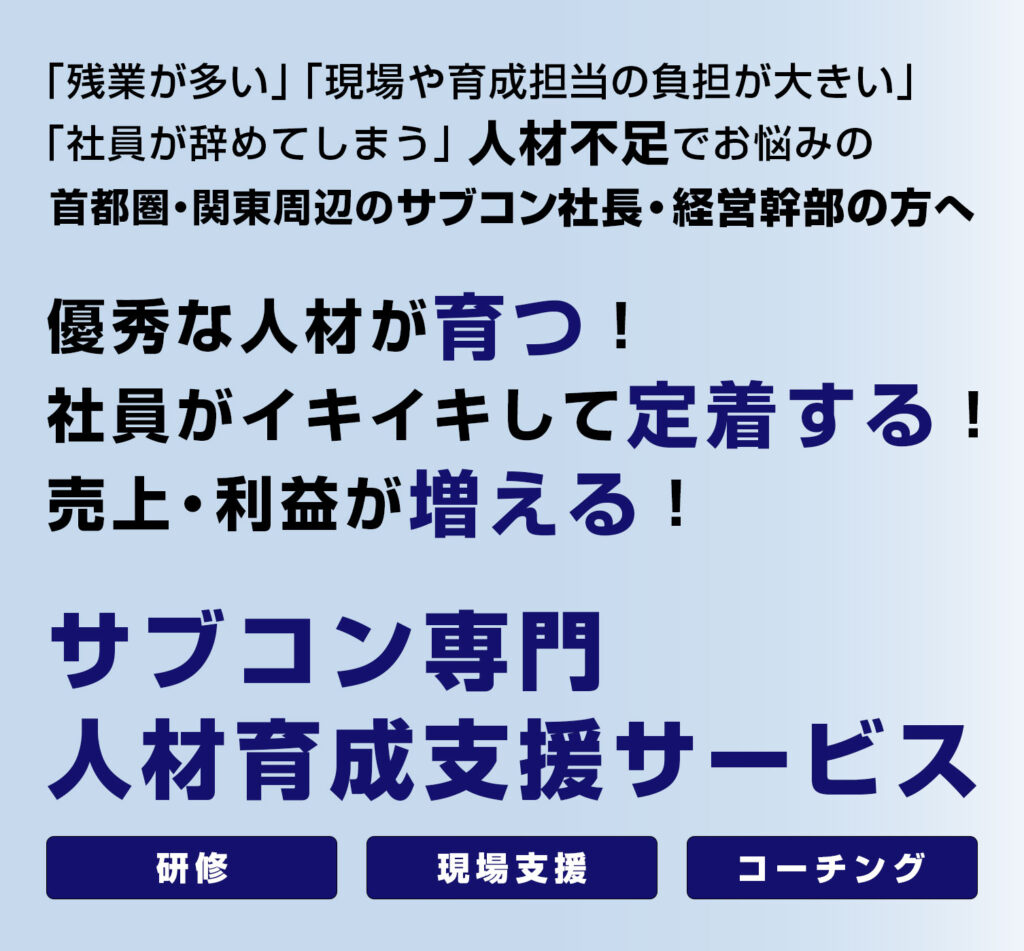
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。