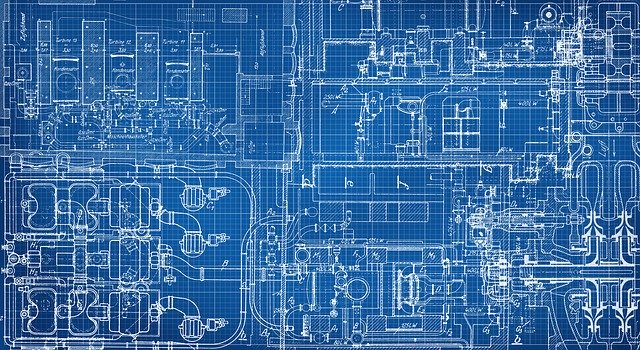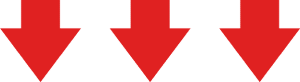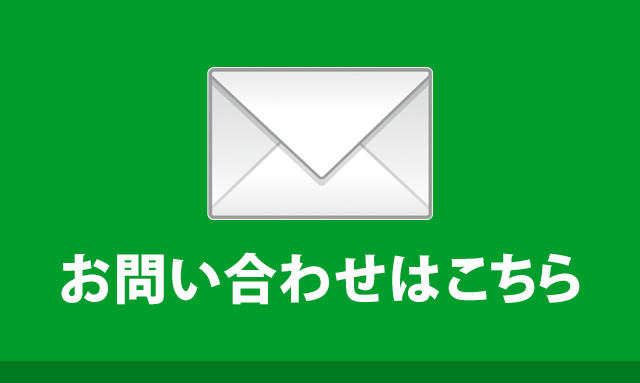空調設備の施工図を書く上で、注意したいポイントを3つ紹介したいと思います。
例えば、経験の浅い社員に施工図を書かせる場合、設計図をそのまま鵜呑みにして、ルートや配置を設計図の通りに移すことをしてしまいがちです。
事前に施工図作図の要領や注意するポイントを教えてあげると、時間をかけて作図した図が使い物にならないということも少しは避けられるのではないでしょうか。
» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
空調ドレン配管のレベルと勾配に注意
設計図では立ち下げ位置が数少ないPSに限られ、空調ドレン配管が広いエリアを延々と横引いているケースが見受けられます。これでは、いくらドレンアップを搭載したエアコンでも、勾配が取り切れずに天井すれすれになって納まらないということになってしまいます。また、梁貫通の構造制限で梁下部の貫通穴が明けられる限度があるため、そこでも
高さに余裕が無くなってきます。
空調ドレン配管は、特にレベルと勾配には注意し、配管途中で天井に納まらない場合は、
新たに配管囲いを建築で設けてもらい、そこでドレン配管を立ち下げることを提案することも一法です。

機器のフィルター引き抜きスペースを考えよう
天井埋め込み型のエアコンやロスナイはフィルターやエレメントのメンテナンススペースを考えないで施工図を書くと後々やっかいです。うっかり梁の直近にセットしたりするとフィルターが引き抜けないという問題が発生します。天井が貼り終わって、いざフィルターを入れようとしたら、長すぎて入らないということにならないように、施工図段階で
メンテナンススペースを確保するように、若手社員には指示しましょう。
それと同様に、点検口の位置も施工図に書き込んでおき、点検可能な位置で天井伏図に反映することも必要です。
設計図では機器のメンテナンスのことまで考慮していないので、設計図では見えてこない
施工的な考え方を作図前に教えることが重要ですね。
ダクトの分岐や接続方法は静圧計算を学習することで理解する
設計図上で書かれているダクトの分岐や接続方法は、単純な単線での表記になっていて、
いざ施工図化しようとすると、どう作図すればいいか迷っている若手社員の方も多いのではないでしょうか。
メインダクトから分岐する場合、風量のバランスや滑らに風を送るため、「ダキ」にした方がいいとか、「ドン付け」でいいとか、正解はあるようで無いというのが今までの私の経験ですが、静圧計算をして数値的に分岐や接続方法がどう静圧に影響を及ぼすかを理解した
うえで作図すると、自分なりの一定の基準が分かるのではないでしょうか。
なので、若い社員の方には一度静圧計算を経験させて、どういう分岐や接続方法のときに
静圧が高くなり抵抗を食うのかということを実感として身につけさせて、施工図作図に活かせるように指導するといいと思います。
まとめ
今回は空調設備の施工図作図のちょっとしたポイントを上げてみました。普段、当たり前だと思っていることでも、経験の浅い社員の方に施工図を書かせると、意外なところで
思わぬミスをしがちです。作図する前に、設計図を部下の社員の方と一緒に見ながら、
「どんなところに注意して書いたらいいと思う?」と聞いてみて、部下の反応を見てあげるのもいいでしょうし、またこのようなちょっとしたポイントを事前にレクチャーすると、
手戻りなく作図を進めることができるのではないでしょうか。
「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ
シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。
まずは、資料請求をしてみてください。
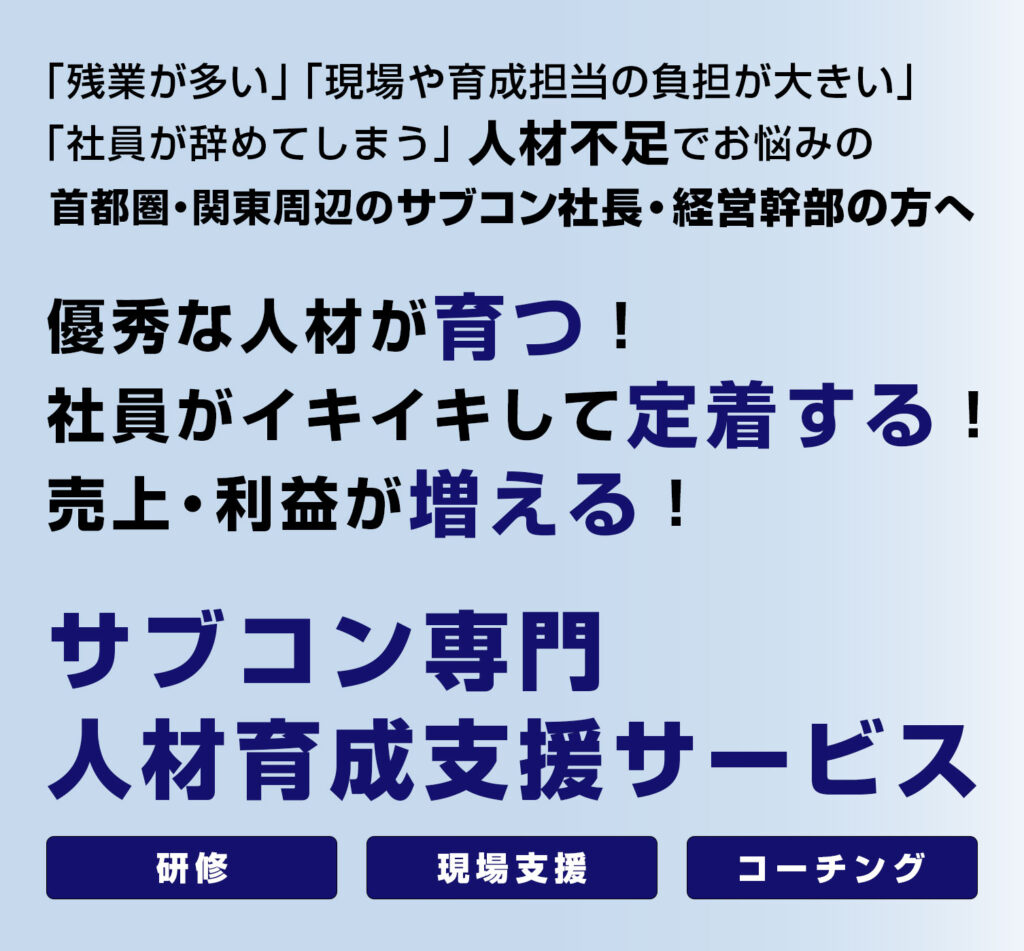
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。