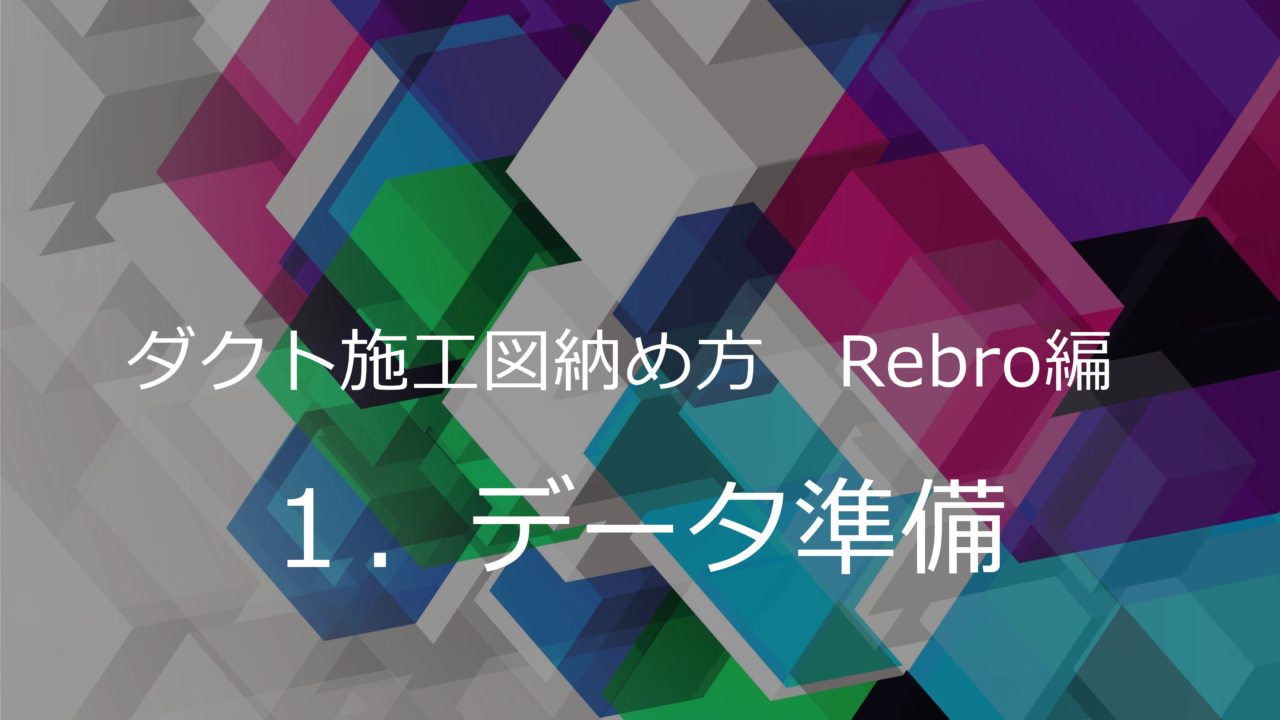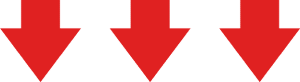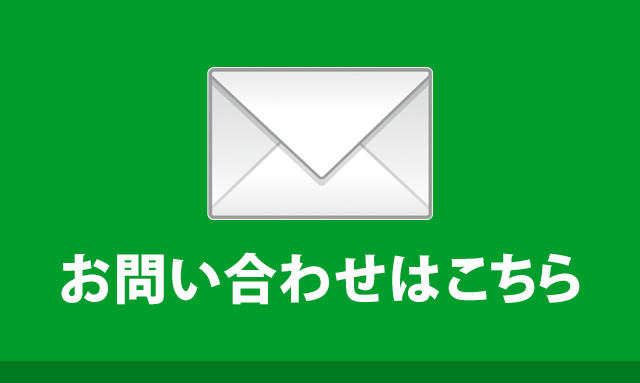私がお手伝いさせていただいている、クライアントのサブコンの担当者の方から、こんなお話をいただきました。
「入社5年経っているにも関わらず、まともに施工図が書けない社員が多くいて困っています。外注に頼ってしまい、若手に施工図を書かせない上司にも問題があるのですが、教える時間もないらしく、何か施工図作図のいい教材がありませんか?」というものです。
そんなお悩みを聞いて、私の頭の中でイメージしていたのが、「納まる施工図が書ける作図の解説動画」が作れないか、ということでした。
» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
目次
CADソフトのマニュアルでは限界がある
T-fasやRebroなどの建築設備のCADソフトには、それぞれの操作マニュアルがあり、テキストだけでなく、動画での操作方法を解説したものがあります。しかし、このマニュアル動画では、そのソフトの操作上でのマニュアルと、例えばダクトならダクト作図のための一般的な一部分の作図手順が説明されているだけです。ですから、ある事務所の天井内のまとまったダクトを設計図を元に一から作図し、梁貫通の構造制限や天井内の梁下フトコロを考え、またダクトサイズをどう変更し、メンテナンスを考え、いわゆる納まりを考えた内容で解説している訳ではありません。つまり、CADの操作マニュアルから、さらに踏み込んだ、納まる施工図を書くためのマニュアル動画が必要になってきます。

施工図の納め方の基礎的なことが分からない
入社して現場経験が少ない若手社員は、施工の納まりについて知識が乏しく、満足な施工図が書けないことはやむを得ません。入社後早い段階で、一人前の施工図を書けるようになるためには、やはり施工経験が豊富な上司の下で教わりながら、たくさんの施工図を書いていくことが理想とされていました。しかし、現場の状況によっては、なかなかそのような恵まれた環境ばかりではなく、上司がいつも近くにいない、いてもなかなか質問する機会がない、そもそも施工図を書く機会が与えられないなど、施工図上達のための条件が
そろわない場合が多いようです
施工図作図要領動画による一通りの流れをつかむ
そんな問題を解決するのが、「納まる施工図を書くための動画」です。今回、弊社で準備している動画は、「ダクト施工図納め方 Rebro編」で、まもなくリリース予定です。
目次をご紹介します。
1.作図の準備
1-1 データの準備
1-2 機器の配置
1-3 制気口・ガラリの配置
1-4 ダクトの複線化
1-5 現状データの確認
2.ダクトと梁・壁
2-1 ダクトが梁・壁と並行
2-1 梁・ダクト同士の干渉
3.梁貫通・梁下の納まり
4.その他の納まりポイント
4-1 メンテナンススペース
4-2 防火区画
4-3 制気口と枝ダクトの接続
4-4 その他の納まり検討
4-5 チェック
以上の4つの章で構成されています。
作図するための準備から、ダクトが梁や壁と干渉していないか、丸ダクトが梁貫通する場合の梁の構造制限から貫通する位置の確認、梁下の天井フトコロの納まり、ロスナイのフィルター引き抜きのためのメンテナンススペースの確保、ダクトの防火区画貫通の考え方、その他の納まり検討方法など、施工図を書くための様々なポイントから解説した動画になっています。また、基本となる技術的な知識が網羅されており、Rebroの操作方法も適宜入れているので、分かりやすい構成です。
この動画を見ながら作図すれば、施工図を初めて作図するという方でも、ダクトの知識を学びながら一通りのダクト施工図が書けるようになります。
動画学習でのメリットと効果
この動画を見ながら作図をすることで得られるメリットとして、2つ上げられます。
一つは、動画の構成が手順を踏みながら段階的に作図できるようになっているので、施工図作図の経験がない方や技術的に知識が浅い方でも、理解しながら書けるようになっている点。もう一つは作図のことで教えてもらう上司の方が近くにいない、またはいても忙しく落ち着いて教えてもらえないという方が、人に教えてもらわなくても自学自習で作図できるようになる点です。
現場の納まりはその現場ごとに違い、「これが正解だ」と言い切れるものではありませんが、基本となる考え方やルールは根本のところでは同じです。その基本をこの動画で押さえているので、それを参考にアレンジしていただけたらと思います。
まとめ
施工図を作図しようと思っても、CADソフトのマニュアルはあっても、一から納まりの
要領を教えてくれる施工図動画というものがありませんでした。クライアントの担当者様の一言で、「では作ってみよう」と思い立ち作成したのが、この「ダクト施工図納め方 Rebro編」です.
ぜひ、作図経験の浅い若い方に使っていただき、一日も早く一人前の施工図が書けるよう
に弊社一同、応援しております。
この施工図動画に興味があるという方は下記にお問い合わせください。
「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ
シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。
まずは、資料請求をしてみてください。
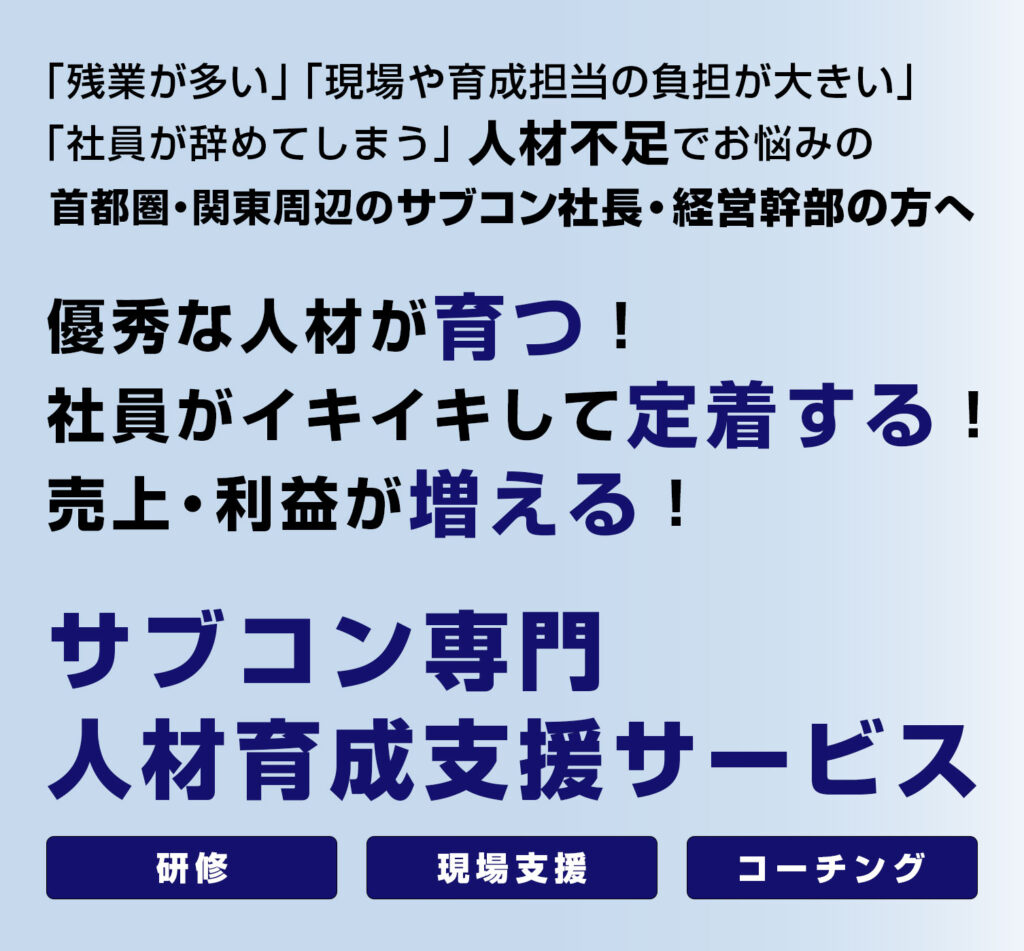
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。