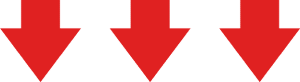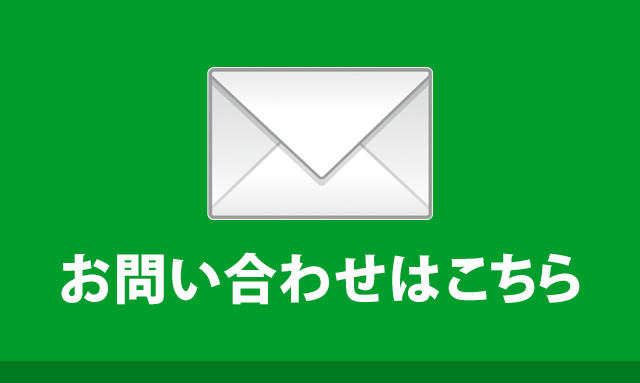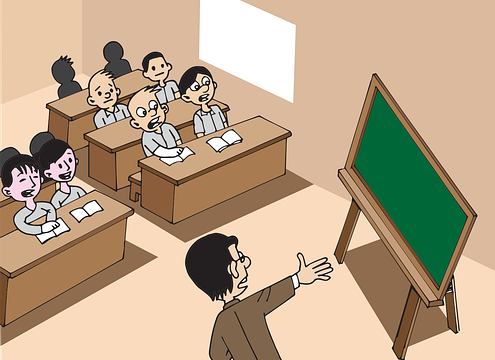アンガーマネジメントが、現場の安全をつくる

» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
怒りをコントロールするアンガーマネジメントとは?
今回は「アンガーマネジメント」がテーマです。
現在はコンプライアンス、企業が法律の範囲に留まらず、社会規範や倫理観などに従って行動することが厳しく問われるようになりました。
しかし、経営者や管理職の度を越したパワハラのニュースは、絶えることなく、枚挙にいとまがありません。
その怒りのコントロールをするのが、アンガーマネジメントです。
怒りという感情と上手につき合うための心理トレーニングであり、多様性を尊重する現代社会において欠かせないスキルです。
1970年代にアメリカで、DVや差別行為などの軽犯罪者への矯正プログラムとして生まれたこの手法は、現在では教育現場や職場の改善、パフォーマンス向上の手段として広く用いられています。日本でも近年、受講者が急増しており、医療や福祉、スポーツ分野などでも導入が進んでいます。
特に注目すべきは、働き方改革や多様性の推進とアンガーマネジメントの関係です。国籍、性別、年齢、価値観が異なる人々が共に働く環境では、他者の違いを受け入れる姿勢が必要です。しかし、旧来的なパワハラ文化が残る職場や、感情を抑えきれず怒鳴る社員がいる環境では、多様性は定着しにくくなります。
特に、中高年層の管理職が若者の感覚を理解できず、強権的に振る舞う職場では多様性の実現は難しいとされています。
怒りの感情をコントロールできないことで生じる弊害は多く、部下との意思疎通が不十分になり、同じミスを繰り返す原因になります。また、怒りは集中力や思考力、判断力を奪い、心身にストレスを与えます。アンガーマネジメントを学ぶことで、こうした悪循環を防ぎ、心身の安定や疲労回復にもつながるのです。
具体的なトレーニングとしては、怒りを感じたときに「6秒間待つ」ことが効果的です。6秒あれば人は冷静さを取り戻せるとされ、怒りを温度として数値化することで客観的に感情を把握する力が養われます。また、「思考のコントロール」も重要です。出来事を「許せる/許せない」と2択で判断するのではなく、「まあ許せる」という選択肢を加えることで、多くの事柄が受け入れやすくなり、無駄な怒りを抑えられるようになります。
アンガーマネジメントは怒りを我慢することではなく、適切に表現し、冷静な行動につなげるための技術です。多様な価値観が交錯する職場において、自分以外の考え方を認め、成長につなげるためにも、誰もがこのスキルを身につける必要があるといえます。感情のコントロールこそが、真に信頼されるビジネスパーソンへの第一歩なのです。
<参考文献>
ダイヤモンド・オンライン:「パワハラ慣れした中高年管理職に必須、アンガーマネジメントは健康
にも効く」

怒声のない現場が、安全をつくる
それでは、今でも一部で残っている建設現場におけるパワハラ体質をアンガーマネジメントで改善する方法を考えてみました。
このような体質が一部で残っているのは「厳しさが当たり前」、「怒鳴ってでも仕事を覚えさせるべき」といった古い価値観に根ざしていているからです。確かに、命に関わる仕事であるがゆえの緊張感や迅速な指示伝達は必要です。しかし、怒りや威圧を手段として使い続ければ、職場の人間関係は徐々に壊れ、生産性や安全性すら損なう結果となります。
そのため、まず取り組むべきは「怒り=悪」ではなく、「怒り=情報」と捉える新たな価値観を現場に根付かせることです。怒りは、自分の価値観が脅かされたときに生じる自然な感情ですが、それを爆発させるのではなく、どう扱うかが問われます。
その第一歩として、「怒りを冷静に見つめる習慣」を作ることが重要です。例えば、「なぜ自分はあのとき怒ったのか」「本当は何を伝えたかったのか」といった問いかけを、日々の中に取り入れます。
これにより、怒りの原因を自覚し、反射的な怒鳴りや人格否定を避けるようになっていきます。アンガーマネジメントの「6秒ルール」も有効です。怒りのピークは6秒間。たったそれだけの時間を意識的に深呼吸や間を取ることで、衝動的な言動を抑えることができます。これを「現場の安全行動の一つ」として位置づければ、受け入れられやすくなります。
次に重要なのは、現場責任者など、影響力のある立場の人への教育です。多くのパワハラは、部下を育てたいという気持ちからくる誤った表現に起因します。叱ることと怒ることの違い、そして「相手を尊重しながらも厳しく伝える技術」を、現場の言葉に落とし込んだ実践的な研修によって身につけてもらいます。このとき、ただの理論ではなく、実際の現場で起こりうるシーンを用いてロールプレイ形式で体得させることが大切です。
また、現場全体の風土として「承認文化」を広げることも欠かせません。怒りの根底には「わかってもらえていない」「評価されていない」といった不満があることが多く、それを解消するには、小さな行動や成長に対するポジティブなフィードバックが効果的です。「ありがとう」「助かった」「いい判断だったね」といった一言が、怒りを予防し、チーム内の信頼関係を深めます。こうした声かけは、現場朝礼やチャットなどに仕組みとして組み込むことで、自然と習慣化されていきます。
さらに、組織としての姿勢も重要です。「怒鳴る上司は評価されない」「人を萎縮させる指導は認めない」といった明確な方針を、経営層や現場責任者が発信し、行動で示していく必要があります。建設現場においては特に、上層部の姿勢が現場の空気に大きく影響を与えるため、トップダウンでの意識改革は非常に効果的です。
そして忘れてはならないのが、若手や女性など、多様な人材が安心して働ける環境づくりです。怒声が飛び交う現場では、新人は「質問しにくい」「間違いを隠してしまう」といった行動に出がちで、それがかえって事故や品質低下につながることもあります。心理的安全性の高い現場は、結果的に安全性・品質・定着率のすべてにおいて優れた成果をもたらします。
以上のように、パワハラ体質の改善には、怒りに対する新たな理解、行動習慣の見直し、教育体制の整備、承認文化の醸成、そして組織の明確なメッセージが求められます。怒らないことを目指すのではなく、怒っても関係性が壊れず、前向きな行動につながる現場づくりこそが、これからの建設現場に必要な変革なのです。
まとめ
会社のパワハラをなくすためには、建設現場に留まらず、社長や経営陣が「パワハラを許さない」という明確なメッセージを全社員に発信することが大切です。そして、自らも怒りに任せない言動を徹底するのです。これが組織文化を変える第一歩です。
次に、管理職へのアンガーマネジメント教育が必要です。怒りの感情に振り回されず、冷静に対処するスキルを全管理職に研修を通じて習得させる。
そして、パワハラを見過ごさず、社員が安心して相談できる窓口(外部相談窓口含む)を設置し、実際に機能させます。加えて、加害者には指導・再教育を行い、必要なら配置転換も検討します。社長の本気度が伝われば、組織風土は必ず変わります。
弊社、シエンワークスでは、建設業に合った「アンガーマネジメント研修プログラム」を提供しています。詳しい内容をお知りになりたいという方は、下部の「お問い合わせはこちら」からご連絡ください。無料相談を実施しております。
「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ
シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。
まずは、資料請求をしてみてください。
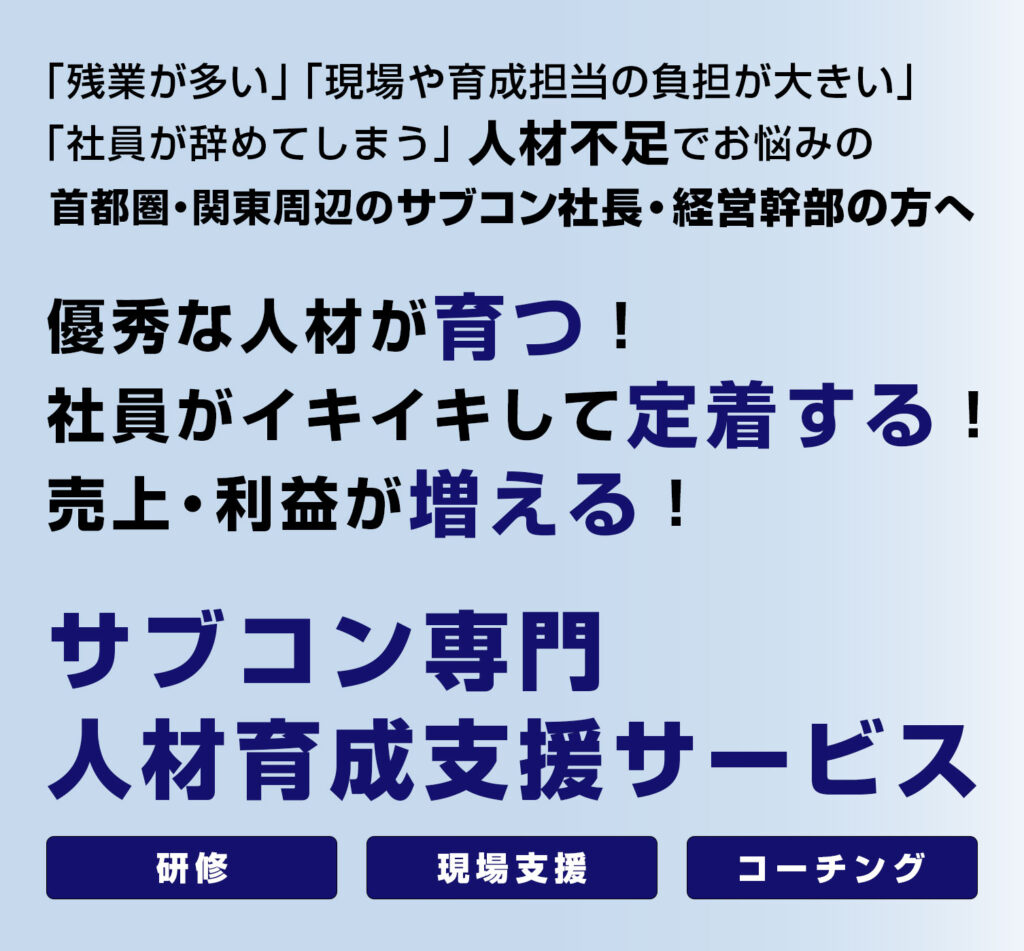
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。