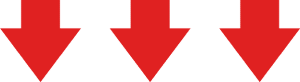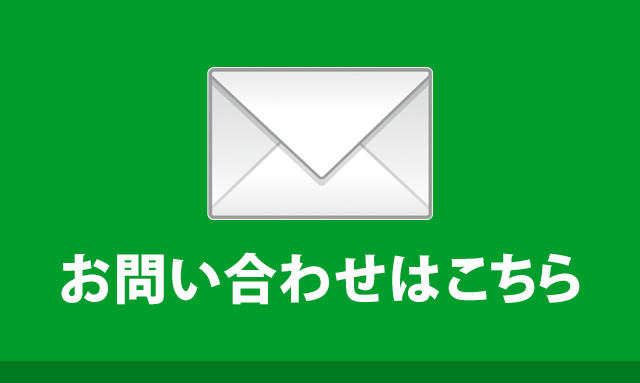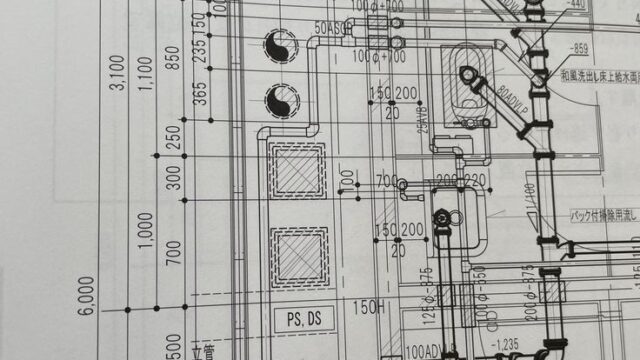» 優秀な人材が育つ!定着する!売上が増える!『サブコン専門 人材育成支援サービス』とは? «
目次
「伝えたつもり」をなくす 医療式コミュニケーション方法
今回から3回シリーズで「医療現場の事故ゼロの取り組みを建設現場に」として紹介します。
建設現場では常に事故ゼロを目指していますが、現実には事故は起こり続けています。
そのため、異業種の事例から学べないかと考えました。
今回は医療現場の事故ゼロの取り組みとして、米国医療研究品質庁(AHRQ)が開発したチーム医療トレーニングのコミュニケーション方法を説明します。医療現場と建設現場は一見まったく異なる世界のように見えますが、どちらも「チームで命を守る」「一つの判断ミスが重大事故につながる」という点では同じです。これを建設現場に応用した形で考えてみました。
TeamSTEPPS/SBAR(定型コミュニケーション)
医療現場では、命を扱うチームが多職種で動いています。医師、看護師、薬剤師、技師などが情報を共有するときに、あいまいな伝え方をすると、たった一つの言葉の違いで患者の命が危険にさらされます。そこで使われているのが「SBAR(エスバー)」という伝達の型です。
たとえば「患者さんの血圧が急に下がっています(S:状況)。昨日から発熱が続いており(B:背景)、感染症によるショックが疑われます(A:判断)。点滴量を増やして主治医に報告します(R:提案)」というように、誰が聞いても分かる順序で伝えます。
建設現場では、同じように多くの職種が同時に動いています。監督、職長、作業員、重機オペレーター、協力会社が入り交じる中で、「伝えたつもり」「聞いたつもり」が事故の引き金になることがあります。
もし職人の一人から職長に「グラインダーに異音がする」とだけ報告されても、受け手によって危険度の判断が異なります。そこにSBARを取り入れると、「グラインダーに異音があります(S)。昨日は問題なかったですが、今日は特に使用頻度が多いです(B)。ベアリングが摩耗しているか劣化している可能性があります(A)。作業を止めて確認したいです(R)。」というように、誰が聞いても状況を正確に理解できます。つまり、“型を共有する”ことで、言葉の伝達を安全の武器に変えることができるのです。

「報告の型」を体で覚える ― 朝礼から始める安全コミュニケーション
建設現場でTeamSTEPPS/SBARの考え方を定着させるためには、「座学で学ぶ→現場で練習する→チームで振り返る」という3段階のトレーニングが効果的です。
医療現場で生まれた手法を、建設現場に合わせて実践することで、言葉の行き違いや思い込みによる事故を防ぐ“安全文化”を育てることができます。その具体的な進め方を説明します。
TeamSTEPPS/SBAR(定型コミュニケーション)のトレーニング例
まずは、「伝え方の型」を体で覚える訓練から始めます。
建設現場では、朝礼や危険予知(KY)活動の時間を使い、「SBARで報告・相談する練習」を日常的に取り入れます。
たとえば次のようなケースで、職長・作業員・監督がロールプレイを行います。
例:足場の異常報告ロールプレイ
(従来の報告):「グラインダーに異音がします」
→ 聞く人によって「後で直せばいい」と軽視される可能性があります。
(SBARを使った報告):「新人の職人が使用しているグラインダーに異音がしています(S)。昨日は問題なかったですが、今日は使用頻度が多いのと、使い方が不慣れの様子です(B)。ベアリングの摩耗か劣化が考えられます(A)。作業を止めて工具の全数確認をしたいのですが(R)。」
このように、「何が起きているか」「背景」「自分の判断」「どうしてほしいか」を順序立てて話すことで、報告の質が大きく向上します。
また、「逆SBAR」トレーニングも有効です。監督が報告を受けたときに、「背景をもう少し教えて」「あなたはどう考える?」と質問して、相手の情報整理を促します。これにより、“話し方”だけでなく“聞き方”の質も上がり、チーム全体の伝達力が高まります。
さらに、月1回のヒヤリハット報告会で、報告をSBAR形式で発表させると、整理された伝え方がチームの標準になり、「伝えること=安全を守る行動」という意識が根づきます。
定着させるための運用例
これらのトレーニングを一度きりの講習で終わらせず、現場の日常活動に組み込むことが重要です。たとえば以下のように習慣化すると、自然に「考える現場文化」が生まれます。
月1回の職長会議で、SBAR形式の報告発表を行う。
朝礼で「今日の一言SBAR」として、各自が安全注意を伝える。
こうした小さな実践の積み重ねが、「報告の型」を現場の共通文化として根づかせます。結果として、事故やヒヤリハットが減少するだけでなく、チームの信頼関係が強まり、現場全体が“安全で考える組織”へと成長していきます。
まとめ
経営者として大切なのは、「安全は制度ではなく文化でつくる」という姿勢を会社全体で共有することです。まず、社長自らが「伝える力が事故を防ぐ」と明言し、安全大会などでSBARの具体例を紹介することで、現場に本気度を伝えます。トップの姿勢が社員の意識を動かす出発点になります。
次に、この取り組みを一時的な研修で終わらせず、日常の仕組みに組み込むことが重要です。研修でSBARを学び、朝礼や危険予知活動で練習し、月例会議で振り返る流れを制度化します。これにより、報告の質が上がり、コミュニケーションが安全文化の中心に根づきます。
最後に、成果を見える化して社内に広げます。ヒヤリハット報告の質を評価し、良い事例を社内で共有することで、「伝えることが安全を守る行動だ」という意識を浸透させます。こうしてTeamSTEPPS/SBARを単なる教育ではなく、企業文化として定着させることが経営者として大切です。
弊社、シエンワークスでは、建設業に合った「人材育成プログラム」を提供しています。詳しい内容をお知りになりたいという方は、下部の「お問い合わせはこちら」からご連絡ください。無料相談を実施しております。
「建築設備」「施工管理」の人材育成でお悩みのあなたへ
シエンワークスでは、解決のサポートをいたします。
まずは、資料請求をしてみてください。
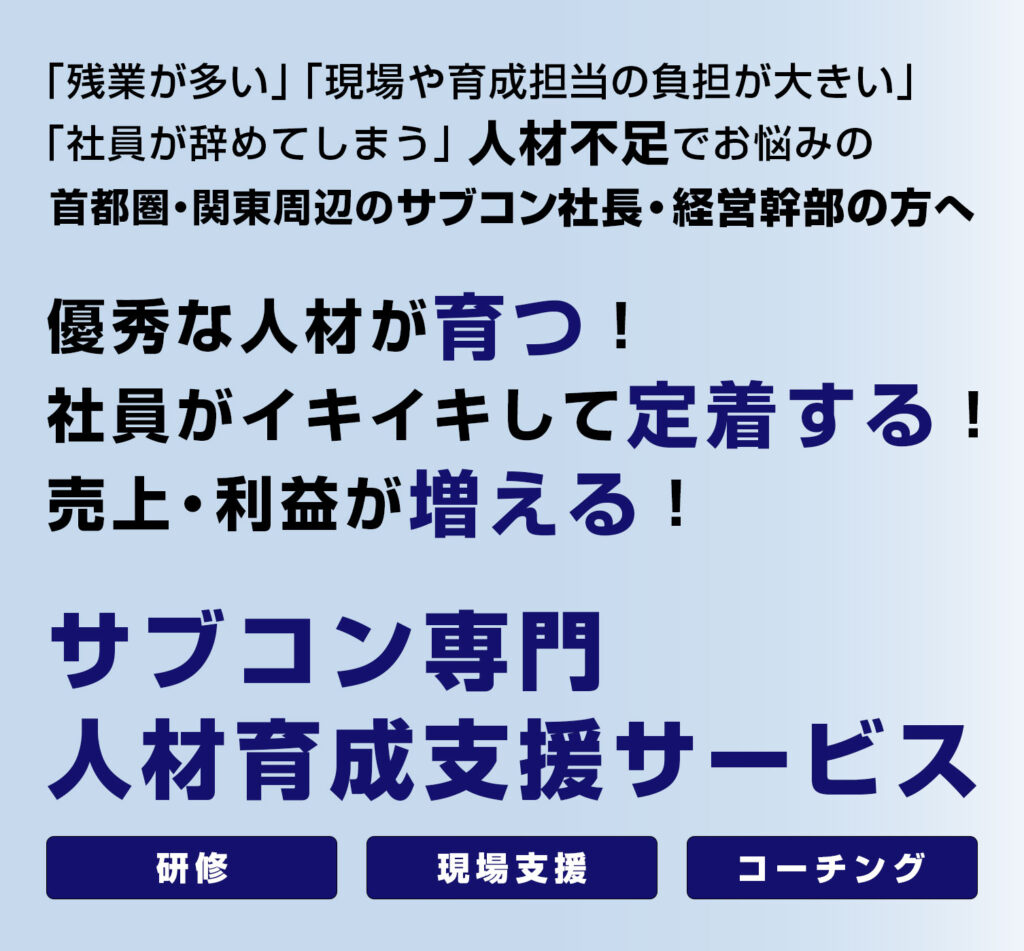
建築設備現場で働く
社員に笑顔を

社員がメキメキと成長し、的確に判断して主体的に動けるようになり、残業や遅延なく業務を遂行できる。
現場も社内もやる気と活気に満ちて、楽しくイキイキと働きながら、無理なく売上・利益が増えていく。
そのような会社を目指されている、サブコン社長・経営幹部の方は他にいらっしゃいませんか?
株式会社シエンワークスでは、
『サブコン専門 人材育成支援サービス』(研修・現場教育支援・コーチング)を通じて、人材の育成・成長、離職率の低減、売上・利益の向上を支援しています。(人材開発支援助成金が活用できます。)
首都圏・関東周辺のサブコン様を対象に、出張&初回無料相談を承っております。
以下より、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。